迫りくる2019年問題「卒FIT」
最近、エネルギー関係のニュースでよく聞くようになってきた「卒FIT」という言葉ですが、エネルギー事業者に取って次の大きなビジネスチャンスとして注目を浴びています。
「卒FIT」ビジネスとは、
・2019年にFIT(固定価格買取)契約が終わる需要家が対象
・これまで旧一般電気事業者と契約していたものをスイッチング(SW)
・余剰電力の買取を新たな買取事業者が行う
ものです。
買取事業者は、現時点(2019/03/08)では正式名称は決まっておらず、
経産省でも「売電できる事業者」という形になっています。
売電できる事業者|資源エネルギー庁
ただし、この「売電出来る事業者」ですが、
「小売電気事業者登録している事業者の中で希望があれば掲載する」となっています。
そのため、ここに掲載される事業者はすべからく小売電気事業者となります。
この「売電できる事業者」の対象を拡大させる議論も過去にはありましたが、現在では「小売電気事業者のみ」という結論に達しています。
卒FITメニューは続々と発表されている
卒FITビジネス=余剰電力の買取メニューはすでに数社が公表しています。
プレスリリース - 卒FIT太陽光余剰電力買取サービスの事前登録受付を本日から開始 - 昭和シェル石油
積水ハウス、オーナーの卒FIT電力を買取り自社事業用電力に有効活用する「積水ハウスオーナーでんき」開始
昭和シェルは北海道/東北/東京/中部/北陸/関西/中国/四国エリアが8.5円/kWh・九州エリア7.5円/kWh、積水ハウスは全エリアで11円/kWhで買取するというメニューです。
一方、旧一般電気事業者は、「買取を継続する」という表明はしているものの、現時点で具体的な買取メニューを公表しているところはありません。
経産省が発表している全体スケジュールでは、2019年6月末までに発表することになっていますので、旧一般電気事業者からの発表はもう少し後になる予定です。
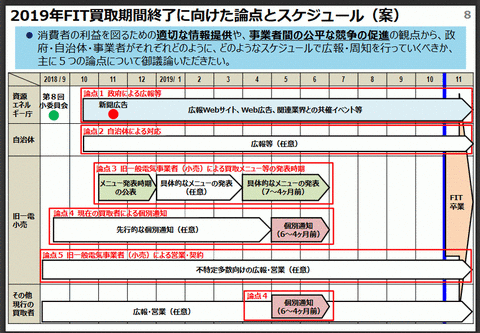
※第8回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会資料より
ただし、同小委員会での中間整理(2次)(2019/01/28)では、
目指すべき再生可能エネルギーの発電コスト7円/kWhを2030年度の目標から3~5年前倒し、2022~2024年度の平均売電価格8.5円/kWhを目指すべき必要があるとしていますので、旧一般電気事業者の発表価格もこれらの範囲に収まるものではないかと考えています。
総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会‐中間整理(第2次)(METI/経済産業省)
卒FITビジネスは周辺ビジネスが狙い
では、なぜ各社はこのビジネスに注目しているのでしょうか。
その理由は「電力調達」と「周辺ビジネス」にあります。
まずは電力調達についてです。
現在、自社の供給量を賄うほどの発電設備を持たない新電力の調達方法は「相対契約」と「JEPX(卸市場)」になります。
ですが、相対契約をおこなう発電事業者の数も発電量も、新電力の供給量すべてを賄うほどではありません。
そのため、現在相対契約の恩恵を受けているのは、一部の新電力になります。
その他大部分の新電力は、JEPXによる調達を活用することになります。
ですが、このJEPXでの約定価格は季節変動が大きく、かつ電力需要が急増した時には異常とも言える価格高騰が発生しています。
今年の冬は暖冬のため、それほど電力需要は上がることなく、JEPXも落ち着いた価格となっていますが、厳冬だった去年の冬には50円/kWhになることもありました。
ここまで約定価格が上がるとJEPXでの調達に依存している新電力は、利益面、キャッシュフロー面で厳しい状況となります。なぜなら日本では、JEPXの価格変動を売価、すなわち需要家に提供する料金メニューの価格に転嫁することができないケースがほとんどだからです。
JEPXの約定価格高騰は、新電力の調達コストアップに直結し、経営を大きく悪化させる要因となります。
その点に置いて卒FITビジネスは、新電力の「調達手段の拡充」となります。
小売電気事業者が買い取った余剰電力は、その小売電気事業者の発電BGから需要BGに卸販売することで、需要調達計画の「調達計画」の一部となります。
太陽光発電であり、発電量が天候に左右されますが、買取契約件数を一定規模確保すれば、JEPXのように価格が変動することがない新電力の有力な調達手段となりうるわけです。
にほんブログ村

コメント